東京ヒップを超えてゆけ!
語った人(五十音順)
・池田宏貴さん
・加藤靖成さん
・神村嘉隆さん
・森順一郎さん

20230501 TOKYO HIP FORTUNE
原点 BEGINNING
The Origin of Almost Everything
始まりの物語は、現在につながる気づきや納得を私たちに示してくれる。
東京ヒップが辿り着いたゴールから、そのスタートと軌跡を振り返ってみよう。
かつて立っていた場所から臨んだ未来は、どんな道を辿ってどんな姿で今ここにあるのか。
答え合わせの先に、次はどんな新しい景色に思いを馳せるのか。
HISTORY

2002年(平成14年)
4月
・東京ヒップ社名決定
(コスモエンドになりかける)
6月
・有限会社東京ヒップ設立
・初受注は共同印刷から
・大日本印刷グループとの取引開始
・大日本印刷から初受注(日本旅行の赤入れ)14万円
2003年(平成15年)
・飯⽥橋へ移転(飯⽥橋ISビル7F)
2004年(平成16年)
・アスクル受注(500h/月くらい稼働したけど明⽇は来なかった)
2005年(平成17年)
・旅ルーム受注
・K村さんが失禁するほどの⼤炎上
2006年(平成18年)
・株式会社アベニーダ設⽴
・津曲さんがアベニーダへ異動
2007年(平成19年)
・杉野さんが派遣されてくる
2008年(平成20年)
3月
・ダイエー受注
8月
・株式会社に商号変更
11月
・神村嘉隆が取締役社⻑に就任
「もともとヒップをつくった理由は不純だったんですよ」
森はそう振り返る。
凸版一社で90パーセント以上のシェアに安住することに対して井上会長は不満を感じていた。
しかしすぐにそれを打破する方法など見つかるはずもない。
そこで動いたのは当時営業の先鋒にいた津曲敬夫だった。
飯田橋ISビルで臨んだ景色
加藤 最初から大日本の話あったかな。
神村 俺にはなかった。
森 まず俺、そんなこと考えてるって話を聞いて。
森 先方と知り合ったのがきっかけで、これ持っていけるな、と話がとんとん拍子に結構進んで。じゃあメンバーどうするって、そういう不純な理由ですよ。最初は秋葉原の秋洲ビルの中に島をつくって、パーテーションで区切ってやるかと考えてたんですけど、それは駄目だろって言われて。せめて会社を分けられないかっていう、そういう話。えいやっでやっちゃいましたね。津曲さんがあんな感じだったから、変えちゃうほうがいいっていうのを、じゃあ進めますよみたいな感じで。
—— トップシークレットというよりも、勢いだったのかな。
森 そこら辺、分かんないです。どのタイミングで加藤さんに話が伝わってたか。
加藤 ずっと後だろうね。年表見ると、2001年が長崎屋、ダイエーショック。2002年に東京ヒップ設立してますから、秋洲ビル3階のダンク事務所内にて事務所開設してるんですよ。
神村 最初はね。
森 すぐには立ち上げられないって先方にも言って。ただ、すぐに部屋借りてやりますとも言ったんじゃないすかね。
大ピンチのときに新会社。「どうする俺たち」
—— この状況で新しいことをやるって言われても思考停止しちゃいますね。
神村 何それって。大日本をやるんだよっていうのを、先に言ってくれれば断ったかもしれないし、もし言われてたとしてもそんなに悩まなかったかなとも思う。何やるかを考えることに、すごい悩んだんで。
—— 津曲さんの立場で考えると、現状を守る見方と将来を切り開く見方、両方があったのかも?
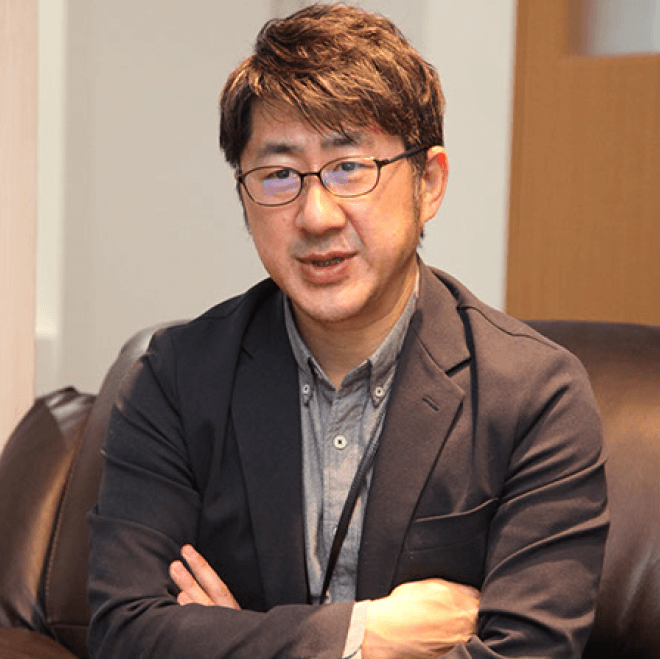
加藤 会長の意図は、そこだったはずですね。決して大日本をやりたいわけじゃなかった。ヒップはいろいろ楽しいことやりゃいいんだよ、みたいな。
—— 「新しいことを」っていう方向性だったんですね。
加藤 当時の東京ヒップの事業内容を見ると、ありとあらゆる事業が入ってる。映像も入ってるし。本当、津曲さん、何でもありだなっていうぐらい入ってた。でも、そういうところを目指してたんだろうなっていう気がします。
神村 そのときはまだ、池田さんとかもいたのかな、ユニー以外のチームが飯田橋のISビルに入ってて、わしらとかイトウ君とか、シミズ君とか、とかが、凸版のビルに入ってたんです。そのときに話聞いたんじゃないかな。何それって。ダイエーの話も聞いてないから。長崎屋がなくなって、いろんなでかい仕事がなくなって。会長も人がいいから、その人たちを辞めさせないで、ちゃんと他のチームに分けてたんだけど、どう考えても人余りしてる感じだった。そんなときに新しい会社つくるよって話だったから。
—— 大ピンチの時に、新しい&楽しい領域の模索が始まった。
神村 ダイエーとかやりたいんだろうなとは思いながらも、凸版がダイエーほぼ失注。今、話にあるとかしかやってなかったんじゃ。
加藤 レギュラー取られて、そんな気もするね。医療PAとか、家電PAとかそういうレギュラーチラシに対する企画チラシ。
神村 そんな状態のときで、ぶっちゃけると本当にこの会社は終わるんだなって、俺はちょっと思った、そのとき。
加藤 ダンク自体がね。
神村 うん。一応あがきとして、新しい会社だって言ってるみたいな感じで。ダイエー以外とかで、今いるスタッフを全員何とかするわけにはいかんだろうっていう感じは、肌感で何となくあったんで。
加藤 当時、ダンクが一番人数多かった。120か130ぐらい。そこで増えたのも、長崎屋のチームをつくるためだったけど。それがなくなったんだよね。何年やったかな。
神村 1年半とか2年ぐらい。下手すると2年やってないような気がするな。
加藤 だから経営史上、大ピンチ。そこで会社をつくるっていう判断をしたんですよ。
ダンクとヒップ、それぞれのミッション
加藤 チラシ全盛のときなんですけど、経営視点では、新しいことを始めなきゃいけないなとか、企画もできなきゃ駄目だとか、そういういろいろな危機感があった。あとは、大きくなっていく会社をちゃんと考えていく必要もあった。でもみんな作業のことしか考えてなくて。会社ってものを考えてかないと駄目だっていう意図で、そういう選抜部隊をつくった。
—— それはいつ頃だったんですか。
加藤 ヒップより前。
—— それはヒップには引き継がれなかった?
加藤 そうですね。
—— ヒップとの違いは何だったんですか。
加藤 津曲さんがいなかった笑。ダンクは割と一つの仕事で、がっぽがぽ稼いでたんですけど。
神村 あのとき、津曲さんどこにいたの。秋葉にいたのか。
加藤 そうだね。
森 カタログとか見てた。
加藤 チラシ全盛のときなんだけど、津曲さんはカタログとかにも営業かけて、獲りに行って、って感じだった。
神村 結構いろいろやってたんだ。
森 やってた。結構流れてたよ。
加藤 デザインチーム作ったの、いつだったろう。
神村 デザインチームは、元からある。
森 俺が入社するときからあった。
加藤 Dマートからあるか。

神村 俺が入ったときからデザインチームはあった。
—— 当時からダンクは制作視点でワンストップでやれていたということですね。
神村 森さんもそうだったと思うけど、入社してDマートの校正をやるってなって。でもダイエーは校正とかだけだし。当時ユニーでは校正だけだったのに対してDマートはデザインもあった。デザインのほうも見とかないと、全然回らないみたいな感じだった。
新しいことに出会えなかったことで出会った、ヒップの「トータル管理」の原点
—— そうなんですね、制作も含めた進行管理視点。
神村 入稿のタイミングまでトメと一緒に動いてたり、あとは上がってきた製版の対応やってたけど、いろいろ面倒くさいことをやってた。あれがヒップの進行管理の原点、みたいな感じはするかな。
加藤 神村さんはダンクとヒップの線引きがないっていつも言いますね。
神村 東京ヒップが新しい会社だとか人間が変わったとか思ってないし。やってること自体はダンクでやってたことをヒップもやってるし。お客さんが大日本になったという、それだけだった。これはダンクでしょって思っていたんです。ダンクでも能瀬さんは出向してたし、トメさんはデザインもしてたし、内田さんは原稿整理もしてた。俺もお客さんの所に行って色校の話を聞いたり、そういうのもやってた中で、ヒップでやってることはダンクじゃんっていうのは、ずっとあった。ちょっとヒップからダンクに戻ってきたら、むしろそこら辺が縮小して校正ばっかりになってて。
池田 ヒップがダンクじゃんってずっと言ってるのは神村さんですけど、ダンクの頃から校正以外の面倒くさいことを元々やってた人だからなんでしょうね。ダンクでそういう動きは神村さんが無二でしたけど、神村さんみたいな役割をやる人を増やしたのは、ヒップですね。
神村 そうなんだろうね。俺の後は、森さんやってたから、Dマート。
森 Dマートね。
池田 津曲さんに引っ張られたんじゃないですかね。制作周りのハンドリングも含めて、ディレクターとして立ち回れそうだというので。

森 Dマートやれって言われたときに、てっきりDマートの校正やれって言われたと思ったんですよ。ところが制作で。神村さんの跡を継いでくれって。絶対無理と思った。デザイナーって面倒くさいんですよ笑。その人たちに校正紙面を落として、それから3人ぐらいいた編集に原稿渡して。要は橋渡しですよね。当時は人がいなかったんで、さらに校正もやるんですよ、自分で。絶対嫌だと思ってたんですけど、1年ぐらいやったんです。最終的にはやってよかったんですけど、まあしんどいですよ。でもあの経験がなかったら、多分東京ヒップに行って、ディレクションとか進行管理って言われても、ぽかんとしてた。チラシってやることたくさんあるんで、いわゆる最大値の経験ですよね。
森 最大値を一応は経験したんで。ちなみに「ヒップでディレクションを」って言葉、俺、大嫌いです。いまだに嫌いなんです。
—— なんでですか。
森 本来僕らは「靴磨きなんです」みたいな仕事です。ディレクター、プロデューサーって、そう簡単に名乗れるほどディレクションって簡単なことじゃないと思うんです、っていう自分の単純なイメージなんですけど。
—— 責任感かな、そう言えるのは。
森 本当難しいと思いますよ。
ヒップで模索した営業の方向性
神村 ルーティンの仕事がなかったんだよね。常に毎回新しい、何カ月の仕事なんで。数字が安定しないし、やってるほうも疲れてきちゃう。
加藤 コンペでしたし。それで十何万もらったところで、大の大人4人がどうすんじゃっていう話で。イメージ的には、ヒップが新しいことをやろうとしたけど、なかなかできない。だけどお金は稼がなきゃいけない。だから、大日本に行ったっていうイメージを持ってました。
—— シマノはメーカー直取引でした。ハウスエージェンシー的なことも狙ってたのかなと。
森 イベント会場回って、名刺交換して、その後あいさつして、みたいなことをやってたんですけど、結局売れるものって校正校閲とか、デザインとかだった。
神村 紙のね。
森 面白いこと、新しいことって何なんだって、思い付かないまま終わっちゃいましたよね。
神村 紙鉄砲だけだったね。
加藤 扇港産業、何の会社だったんだろうね。
森 光ファイバーとか研磨機とか。
加藤 要は印刷会社じゃないお客さんだよね。そういうところからもらった仕事で、イベントの手伝いをさせてもらった。そのときにイベント集客のツールが欲しいっていう話から池田さんが提案した。
池田 名作です。
加藤 紙にいろいろ広告が書いてあって、それを折ると紙鉄砲になる。
池田 イエスノー式になってて、そのとおりに折ってくんです。そうすると紙鉄砲になって。
神村 会場でパアン。
池田 説明会が外国人向けだったので、紙鉄砲はいいんじゃないかって。
森 すごく面白かったですけど、その会社は世界に支社があるんですよ。外国で使ったら本当に撃たれるってやつで。海外で絶対使えないっていう笑。
加藤 危ないからね、なかなか。
—— そのアイデアはどうやって生み出したんですか。
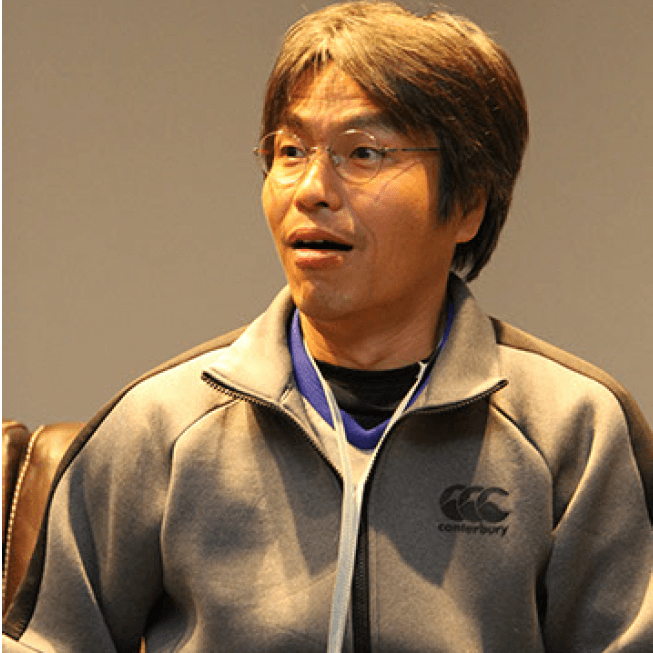
池田 メインターゲットが海外のお客さまというので。前から工作かなんかやってましたよね。漢字をモチーフにして。
加藤 和のテーマはちょっとあったんです。
森 日本っぽいものをって。
池田 当時ググって検索とかほとんどなかったので、「和」か、って。紙鉄砲じゃないですか?って。
池田 先方担当がいいじゃんって、それにしようって。
森 担当も若かった、当時。発想が、面白いもの大好きだった。20代にして発注権があった方なんで、面白いですねって、結構悪ノリが通じた。扇港産業の仕事、面白かったな。
—— トップクリエイターとトップディレクターみたいな人たちがいて、そことセッションできることはリーチでしたね。データで比較検討とかだけじゃなく、密な打ち合わせと新しいものやろうぜという空気や人のつながりは貴重。
加藤 ありがたいお客さんだった。扇港産業さんへは、いろんな人にあいさつ行ったよね、うち。名刺交換とかもしてない人たちが、あれ営業部だけでした?
森 営業ですね。
加藤 先方の営業に池田さんも行った。昨日まで校正してたのに、今日は営業としてスーツ着る、お客さんのところ行って名刺交換する、打ち合わせやる、みたいなそういう感じだった気が。
森 きっかけは、デザインできますかっていう電話だったらしいんです。最初は津曲さんが担当してた。いまだに覚えてるんですけど、結構きれいな女の人だったんですよ、担当の方が。それで津曲さん、趣味と実益を兼ねて、テニス接待したんです。見積りを提出する前ですよ。見積り作る前に、テニス接待したんです。
加藤 それで相場を聞き出そうとして。さすがだね、津曲さん。
森 それでぎりぎりのところを、幾らだったっけな。50万とか。雑広ですよ。高くないですか、50万ですよ。先方予算が大体50万で、今1社から見積もり来てるのが70万とか言われて。じゃあ50万なら全然できるって、50万でぱあんっとうちの見積もり出してゴールしたんです。津曲さんはそういう、ごりっごりの営業でしたね。
津曲敬夫という男
森 あの人、短気で。最初は取りあえず文句言われないようにやってました。でもそれだけじゃつまんないじゃないですか。指示もざっくりしてるんです。それなのに伝わってないとへそ曲げるから、しょうがねえって自分で考えて、池田君を連れ回して仕事してた。津曲さんから得たものは、気負い過ぎるなとか、そういったことです笑。
—— 割と精神論的な。
森 精神論ですね。当の本人はロジカルだと思ってたんです。でも話を聞いていたら、どうやら感情的。しかし図々しさっていうんですかね、人の懐に入るのがうまかったです。そのベースが物おじしないところ。自分も、ここはものにできるんじゃないかって思って見習ってきました。
加藤 森さんに一番最初に目を付けてたでしょう、津曲さん。営業的な魅力だったのかな。

森 入社してまだ1年もたってないくらい頃。俺、ばかなこと言ったんです。校正を津曲さんから頼まれて、それを戻しにいったときに「森君仕事はどうだ」って聞かれたんです。ずっと不思議に思ってることがあって、一つ聞いていいですかって返した。「この会社って営業いないのに、なんで仕事たくさん来るんですか」って聞いたんですよ。みんな机でがりがりやってるだけで、不思議でしょうがなくて。そしたら「面白いこと言うね、君。そうだよ、うちの会社は、みんなが一生懸命やってくれる紙が営業なんだよ」って。
森 そうですか、みたいなことを言ったら、営業やりたいの?って言ってきたから、別にやりたいわけじゃないですけどって。そうなんだ、みたいな感じから、ひょっとしてと思われたらしいです。それで一番最初に試されたんですよ。そこからは、仕事をお願いされるたびに、一緒に説明しに行こうって言われて。で、先方で俺に全部しゃべらせるんです。後から聞くと、人にしゃべれるのかをテストされてた。何年かたって、津曲さんに「一緒にこういうのやらないか」みたいなことは言われました。俺からすると、他にも向いてる人がいたと思いますよ、たくさん。あの当時は良くも悪くも津曲ワールドだったんで、津曲さんが言ったらそうなっちゃう。ごり押しですよ。みんな言い返せないですもん、怒るから。でもその中で結構噛みついてたのが、この2人(森、池田)だと思うんです。
加藤 加藤よりは神村のほうが好きだった。加藤が一番嫌いだった。置いてかれましたね。この3人(神村、森、池田)は連れて行きましたけど、津曲さん。
—— 津曲さんが池田さんを連れて行った理由は何だったんでしょう。
池田 多分、ラグビーつながりと元気な若者。間接的には、森さんが「あいつがいいんじゃない」って話をしたって聞きましたけど。僕は、当時はもう辞めようと思ってた。それを勘づいたっぽくて「あいつ辞めそうだから、引っこ抜いたほうがいいんじゃないの」みたいなことだった、と。俺はお世話になった会社が新しいことやるんだったら、それが一番いいなというだけでしたね。
加藤 会社のエースだったんですよ、池田。いろいろできるし、動くし、徹夜もばんばんするし。
森 当時何やってたっけ、池田。入社3年目?
池田 ちょうど3年たったとき。3年で動かないとずっと惰性になっちゃうという考えがぼくにはあって、3年で何か新しいことをやっていこうと、石の上にも三年計画を実行してたんです。簡単にいうと、辞めるのが一番早いじゃないですか。でもちょうどそのタイミングで、そういう動きがあるって聞いたので、この会社にいたらもっと他のこともできるんだな、それならはい、やります、ぜひって、すぐ。
森 その頃よく酒飲みに行ったりしてたんです、池田と。こんなこと言うから、生意気なやつだなと思ってたんですよね。自分は入社して3年以上過ぎてから行ったわけですから。何だこいつ?と興味が湧いて、池田君、こういうの考えてんだけど、どう?つったら、やりますって言うから、よかったなと。
池田 何をやるかは知らないけど。何でもいいっすよって。
森 取りあえず新しいことをやるんだっていうことだけを、一生懸命俺が言った気がします。
池田 あんま聞いてないです。
—— 新しいことを一緒にやれそうだという、そこに共鳴した2人だったんですね。
森 元気な若者でしたから。
池田 勢いと、あと一応、根気強いみたいな。
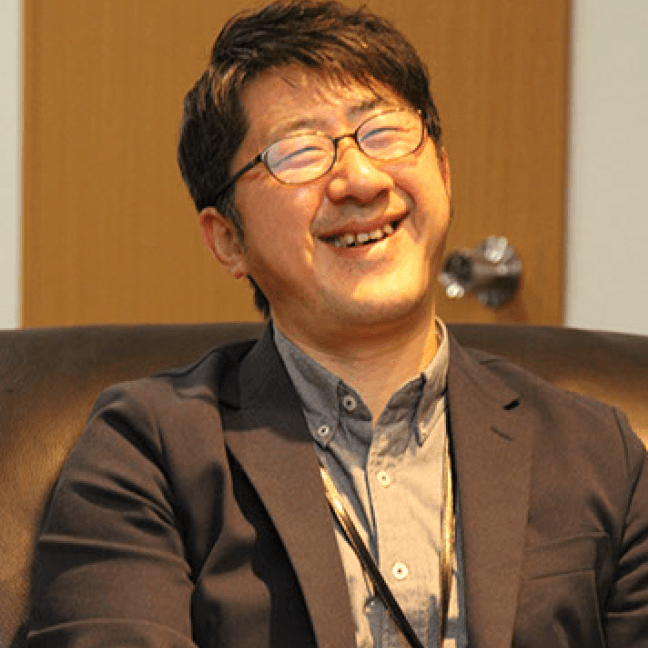
加藤 でも元気のいい仕事できるやつは、全部持っていかれた感じです、当時。俺は、恨みつらみしか。津曲さん、水面下で話進めてて。会長と話つけてうちのチームでやってた手だれたちを全部持っていったっていう感じです、池田とか森さんもそうですけど。俺、入ってないんだと思って、それも頭にきた。俺、津曲さんはもともと苦手だったんです。ごりごり感ですかね。勢いと感情で物事を進めるところ笑。
—— 怒りんぼでゴリ押しじゃ、普通は失敗しますよね。
外に出る、人に会う、仕事につながる
神村 一から営業をするってことぐらいじゃないかな。
加藤 営業会議もあのときからやってたね。森さんや池田さんの電話攻撃とかも。
森 テレアポ・飛び込みはやりましたよ。
神村 俺もしつこく言ってるけど、取ってきた仕事自体はダンクでやってたこととなんら変わってないっていう思いでやってた。似たようなことは内田さんがやってる、トメさんがやってる、みたいな。先方に行って仕事があるかないかを確認取ってくるっていうこと以外は、そんな新しいことしたかな。
森 出向っていうのを嫌わずにやりました。お客さんの名刺持って、お客さんの会社として動くとか。
加藤 それの走りはいつなんだ。
神村 能瀬さんもやってたわけじゃない。
森 でも一部じゃない? 結構それを嫌がらずにやって、数字を上げましたよ。その真骨頂が池田パターン。
加藤 一気に自分に注目させる。腹立つわ。
神村 あとは、派遣さんをうまく使おうとか、外注さんをうまく巻き込んでいこうとかは、ヒップになってから。
森 相手の会社の名刺を持って仕事するって発想、なかったんです。断りたかったですよ。俺、ヒップで一番最初に大日本の名刺持ったんですけど、すごく嫌でした。うちの手柄を持っていかれると思って。自分が一生懸命やったのに「大日本さん、よくやってくれましたね」って言われるから「東京ヒップです」って喉まで出ました。
神村 俺も浜松町行ってるとき、凸版印刷の神村だった。入社してすぐに凸版印刷の人だった。
—— 個人のインプットとしては、どうでしたか。他社の名刺を持ってやったことについて。
森 あんま変わんない。
—— ヒップに持ち帰るぞ、みたいなのは何かありましたか。
森 他社の名刺を持ってお客さんの所に行っても、業務のことじゃないですか、しょせん。それは一過性のものだったんで、あまり自分にぴんとはこなかった。
—— 人はどうでした? 外の人たちを見て。
森 今、僕が話したのは旅行パンフレットの時代の話で、それは業務中心だったんですけど、アスクル、あれはとんでもない経験だった。民族大移動みたいな。ヒップの9割ぐらいが辰巳オフィスにいるっていう。神村さんと数名が、ぽつんと事務所に残されて。

加藤 ダンクからも持っていったよね。
神村 持っていった。
森 うちらが手配したの100人レベルですからね。
加藤 あんな売り上げの仕事って、後にも先にも。
神村 あります(ドヤ顔)。
池田 あんなもんじゃない。
新人の森には、チェックや校正などの仕事が、人が定位置から動かずに決まった場所で粛々と行われていくかのように映っていた。正しさを見る仕事だからこそ、定位置に構えていなければならないかのような。
しかし彼らは外に出ていき、客先の懐に入っていき、やがてその場に欠かせない存在になっていく。誰もが信用・信頼を求めている時代に、彼らはそれを元手に、最も安心安全なトータル管理の座組みを築くフェーズに入り始めた。
正しい仕事を進めることで、場をより良く変える。ついに、これまでにない「新しい」を売り始めたのだ。
後任に負担をかけない池田流引き継ぎ術
池田 歌って踊れる校正マン。生意気な口利く校正マン。このキャッチコピーがあってですね笑。
森 例えば池田が先方に何か落として帰ってきて、担当を外れるとします。大抵、その後そこから仕事の相談が来ますからね。
—— 去った後の穴というか、不在感が大きい。>
池田 不在感はずっと課題だったので、不在感なく去る技も身に付けました。
—— それはどんな?
池田 意図的な部分があるんですけど、去り際にだらしないところを見せる。変わってもらってよかったっていう。そういうちょっとしたことをやっとくんです。
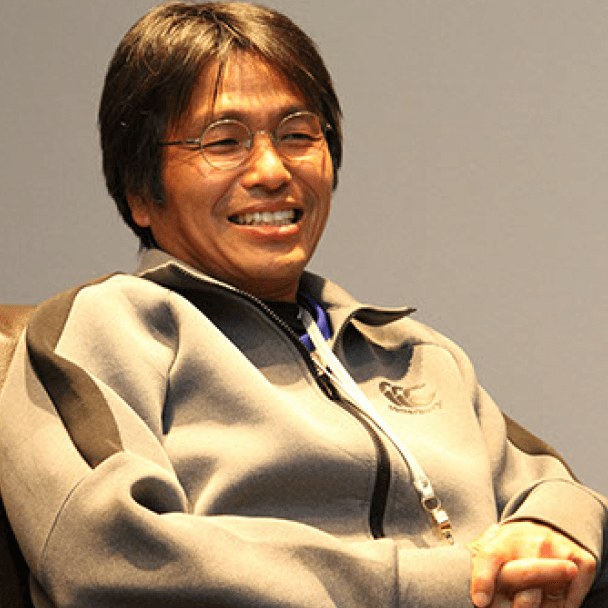
—— 本当に離してもらえない、みたいなことになるから?
池田 というか、ぼくがやり過ぎるとスイッチした人が大変になる。だから新たにやれる状態を残して、渡すんです。「後任さん優秀ですね」となるほうが、お互い去りやすいし入りやすい。
森 はまった?
池田 はまりましたね。こういう感じでいいんだなって。
池田 難しいことはやってないです。うちは器用なスタッフが多いので、基本的に後任は優秀な人が来る。こっちはフルパワーでやる。信じて置いてくだけだと思うんです。
個のパフォーマンスについて
池田 大体、引き継ぐったって、前任やってた人の方ができるのは当たり前ですもんね。これから覚える人がそこを比較されるのは、ちょっと。ハードルを下げとくのは、営業上の工夫です。
加藤 そもそも最初は、仕事を取って増やしていこうって人を投入するんで、池田さんみたいなタイプを入れる。仕事を無事に獲ってもらって、後任に引き継ぐ。するとだんだん……。
神村 引き継いだ人の仕事が消化作業っぽくなっちゃう。
加藤 お客さん側から見ても、うちに営業要素が消えていると、物足りなく感じる人もいるはずだね。評価の高さとも言えるけれど。
森 言われなくても場を見てて、こういうことに困ってるんだなっていうのを、すっと言うやつなんです。それ俺やってみましょうかって。こういうのあったら便利ですよね、俺作っときましょうかとか。そういうことを言われると、誰だってうれしいじゃないですか。
一方、ヒップは新しいことをやろうと試行錯誤を重ねた経験があった。津曲が営業に飛び出して渡したバトンは、彼流のコミュニケーションや営業マインドだったかもしれない。
試されるままに信じて飛び出した先で成長した森、ヒップの節目に自らの人生の節目を賭けて行く先々で実績を残した池田、会社の局面とヒップのトータルな技術力・管理力を冷静に守った神村、ダンクの商流に欠かせないベストメンバーをヒップに託した加藤。好むと好まざるとに関わらず、そのバトンを自分の置かれた場所から受け取って走ったのがこの4人だった。
今や彼らは津曲の臨んだ景色を超えて、その先の道を切り拓き、ヒップのバトンを後進へ手渡すところだ。それは目新しいことでもなく奇抜なことでもない。時をかけて経験を重ね、ヒップの校正の力に新たな定義をもたらしたこと。信頼や正しさの価値を外に持ち出して、そこから起きる化学反応を仕事化するというバトンだ。
紀元前ヒップから誕生した紀元後ミスターヒップ
—— 仕事を数字から見る方に振りきって組み上げていた。
森 見るしかなかったですね。
—— 今までの積み重ねとかフレーム通りの対応で仕事を見るだけではなく、取りたい仕事のためにどんなスキームを組みこむかとか、柔軟な視点が磨かれていったんですね。
森 大抵のことは「どうすればできるんだろう」って、考えるようになってましたよ。そこら辺の幅が出てきたのは、原冨君が入ってきてからです。彼の吸収力は半端ないです、今でもそうですけど。そこで一気にジャンプできた気がしますよね。何持ってきても、大抵何とかしてくれます。そこでヒップの幅が広がってましたよ。だから俺の中ではミスターヒップですよ、原冨君。
—— 私もいろんなお仕事ご一緒させていただきました。原冨さんがいなかったらやれなかったような仕事も。
池田 大東建託ですね。
森 そういうのも、普通だったら音を上げるわけですよ。でも彼は、人をテトリスのように、こうすればはまるかって、きれいに収めるんで。本当に彼がいなかったら無理だった。TFにみんなわあって行ったじゃないですか。中は、ほとんど彼が守ってましたからね。それで相乗効果ですよ、数字の。すごいと思う。
—— 仕事を正しくやるっていうのは、皆さんに共通していましたが、原冨さんはそのフィールドを柔軟に変え始めました。成果物は、物だったり、人だったり、スキームだったり、落としどころはひとつじゃないと。
森 東京ヒップのシーズンは、原冨君がいるか、いないかで別れます。
—— ディレクター、プロデューサー風味の仕事人登場。
森 いろんな人を知ってるんじゃないですか、彼は。だから原冨君が校正現場からリーダーになったんですよ。そこからもうちょっと進んで「営業的な立場にならない?」「いいっすね」っていったところまでが東京ヒップ紀元前です。彼がリーダーになって外を見始めたのが、東京ヒップ紀元後です。それぐらい大きな存在です。ねえ、原冨さん。東京ヒップ後期の話になってきてる、いいですか。
—— いいです。
意外な東京ヒップとダンクの差別化ポイント
加藤 ずっと自分はダンクでやってくって、勝手に思ってましたよね笑。
—— 加藤さんがずっとダンクだと思っていたのは、校正で受ける仕事を拡大したり管理したりする、そういう仕事のイメージがあったということですか。
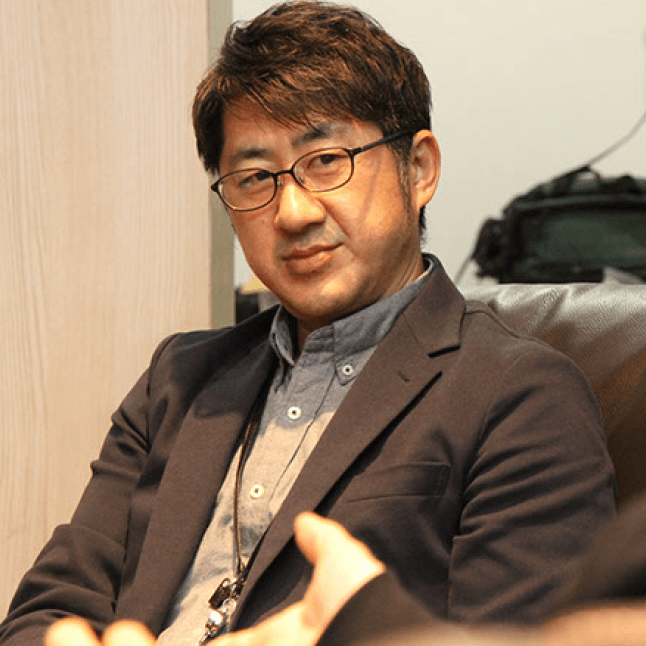
加藤 会社の次の世代だと思ってたので、自分が引っ張ってくんだなって、勝手に思ってたというか。ヒップはヒップで、きょうだいみたいに常に隣にいる感じだけど、ダンクは自分だろうなって思っていました。ダンクの方は校正色がより強くなったのも、自分はダンクでは営業ポジションにいて。数字を考えてうちの商品で一番売れるのは何だと考えると、やっぱり校正になる。その話が一番自信持って話せるし、ありがたいことに、ばんばん仕事も取れたんです。一方で東京ヒップがプロデュース的な動きというか、違う展開見せていったのは、会社としてはすごい、いい流れだったんだろうなと思います。
加藤 東京ヒップではダンクとの差別化をしたくて。ヒップはこうなんだよっていうものを見いだしたかったんだけど、あんまりなかった。そういう意味では、ダンクと一緒だったのかもしれない。ダンクがずっと校正をやってる間に、ヒップが広げていった可能性は、もちろんあると思います。
—— 伝統と革新ですよね。ダンクが仕事の価値を維持して信頼や伝統を守っている。それを同じように知っているし、同じように動けるヒップだから、革新的に動いていった。
加藤 ダンクは王道の仕事ですよね、ずっと最初から。校正は、新しさがいらないというか、そういう意味もありますよね。それ王道だよね、みたいな王道。ヒップは、型を踏まえたうえで、流れを変えたり新しく生み出していく主流というか。
神村 校正に執着するのはやめろっていうのは、会長が言ってたことで。自分としても、確かにそれは吸収して、その認識でやってかなきゃなっていうのがあった。東京ヒップで見ていると、校正だけやっても金になんねえじゃんっていうのはすごいあったし。ところがダンクに行って、ダンクの値段聞くと、なんでそんなにいいの?って感じで。ダンクが凸版からとか、あるいは問い合わせから請ける校正と、東京ヒップが取る校正が、値段が全然違って。
—— そんなに差が出ますか。
加藤 出ましたね。凸版がいかに恵まれていたか。値を崩さずにできてたんです。
神村 ブランディングがうまくいってた。
ダブルチェックは、やらない
池田 ダブルチェックがルールとも思ってなかった。誰が決めたんじゃ、みたいな。
神村 ダブルチェックやらないを最初に言いだしたのは、確か池田さんだったよ。
池田 だって、やってらんないんすもん。別によくねっていう。
—— どんなふうに先方を説得して、カバーしていったんですか。
池田 もともと、ダブルチェックなんて売りにしてなかった。勝手にやって、それでミスってることがあるくらいなら、シングルチェックでも同じ結果出せばいいんでしょっていう話で。
—— それやって、どうでしたか。
池田 いい面と悪い面とがありました。ヒップはシングルチェックみたいなイメージがついて。
—— 全部それってわけじゃないのに。
池田 そういうふうに取り違えられたりもしちゃった。あくまでも、仕事としてはケースバイケースで考えて決めるものじゃないかという選択肢を出したということだったんですけど。
神村 必要なとことそうでないとこ、みたいなね。
池田 前例踏襲で訳も分からずダブルチェックやってるよりかは、考えてミスったほうが成長する。あまりにも考えてないことが多いんで。脱線しちゃうけど、マスクもそうなんですよ。何も考えずにマスクしてるの嫌いで。話もしないのにマスクずっとしてるっていう、要は考えてないっていうのが好きじゃなくて。ぼくはあえて外す。自分で考えてやりませんかと。
—— いい仕事をするなら、何も考えずに型にはまっていてはいけない。
池田 はまっとくほうが楽ちんですもんね。
加藤 ルールを守ってるほうが楽。
—— よく考えて守りながら壊してみようよ、と。
森 全然テーマは違いますけど、マスク最初嫌だったんですよ。でも1カ月ぐらいしたら、逆にマスクがないことに違和感を覚えまして。今、マスクしてるほうが好きです。ほっとするんです。考えてやるって、考えた上でルールを守ることにもなる。
—— 池田さんと森さんのバランスいいですね。その場を見てマスクするかしないか考えるのと、みんなマスクしてるけどその理由はいろいろあるかもしれないって考えるのと。その両方、大事です。
神村 会長が、疑って壊せみたいなところのある人なんで。割とそこは、自分もいろんなことに反発するタイプだから、いいなと思ってて。だからダブルチェックも国井さんがつくったルールだけど、これを本当にそのままやり続けるのがいいのか、みたいな。ダイエーとかやってた頃、時間ないときなんか、最後は見もしねえで入稿して、そのまま終わったりとか……。

森 でも追っ掛けでやってたでしょ。
神村 追っ掛けはやってたけど、2行終わったぐらいで、もういいかってやめたりとか、よくしてたから。
森 それは通常きっちりやってる人が、本質が見えた上で判断することではありますよ。
池田 それは間違いないですね。
池田 その逆もそうです。ダンクでダブルチェックはやるものだから、それについて何も考えてないっていう人は、意味も分からずにやってるという危険もあります。それが何を引き起こすかというと、「うちはそういうものなんで」って、臨機応変な対応ができないかもしれないということ。予算がない仕事だと、うちはそうなんでって考えずに流してチャンスロスしちゃう。
—— 起きそうなことを予測して、その上で割愛するところや挑戦するところをしっかり考える。
森 要は、ダブルチェックで全く同じ流れは必要ない。でもこれだけはやっといてねっていう見極めが必要。単純な話ですよ。
—— これだけはっていうのを、クライアントとか案件ごとにアレンジできるようになっていったら。
森 できますよ、ここにいる連中は。
人を動かし、仕事を広げたり振り分けたりするスキームを動かし、ディレクションや進行管理の仕事を生みだす。それは校正の王道を守ってきたダンクと校正の主流を追い求めてきたヒップの仕事の融合地点かもしれない。
校正から見たディレクションや、校正から見たデザイン・文章など、正解のない社会は、今、そんな機能を求めてはいないだろうか。
これからのダンクが前に進むに当たって、新しい編集、新しい校正の概念を生み出すとしたら。これまでにない視点から仕事の対象を変え、校正の立場も変えていくとしたら。
ダンクはどんな会社になっていくのか。
校正の仕事に新しい視点・概念を取り入れていく
神村 世の中の制作プロセスに関わっている人たち、うちもその中の一つ。全員が全員じゃないですけど、思ったよりみんな、制作のプロセスの中の一つが雑だなっていうのを、どっかのタイミングから思うようになってた。ヒップにダンクが持っている校正の正しさとか丁寧さみたいなのをくっつければ強さになるんじゃないのっていうのは、昔から言ってて。んなわけあるかと思ってたんだけど、今ここまで来て、やっぱり世の中結構雑だっていう感じをすごく持っています。
—— 誰かがやってくれてるだろうとか、ちゃんとなってるはずだろう、みたいなの、いろんな現場で多いのでは。
神村 ていうところでいうと、何かしら売りになっていくんじゃない? そこら辺をもっと強く出せば、商品というか。
—— サービスのね。
神村 売りになっていくんじゃないのかな。もう俺、ぽっこちゃんやってる人だけど。
加藤 校正を進化させようって考えてきたのは確かで。校正というと、校正作業のところにとどまっちゃうんで、会長は編集ってよく分かんない言い方をずっとしてきてるんです。うちがやる編集とは、校正作業も含めた役割なんだよ、みたいな意味合いがあるんですけど。校正を品質管理的な考え方にもうちょっと上げてって、制作にも関わる。もともと校正やってるスタッフはそれをきちんとやっているんで、いろいろ精度も考えます。
—— プロダクトアウトの校正だけではなく、マーケットインの校正という見立てもおもしろいかも。
加藤 うち全員校正やってるんですよ、みたいな。そういうような言い方もできるんじゃないか。そこを売りにしていこうとしてるのは確か。
神村 そこにさらに、伝わるを使う。
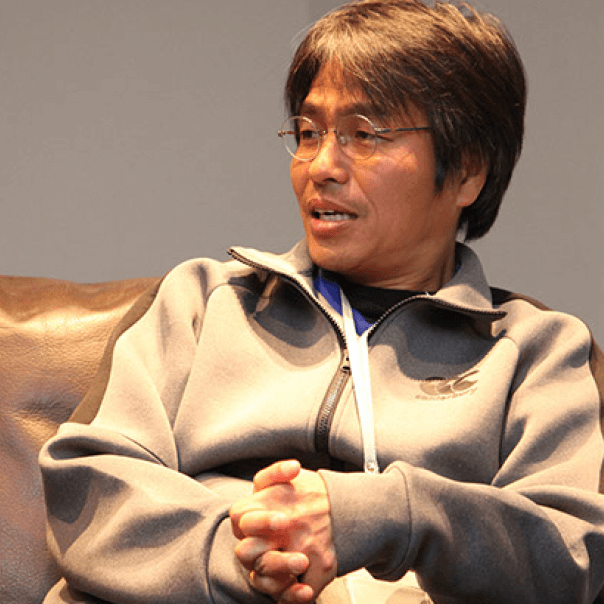
池田 校正の話については熱いものを持ってるんですけど、俺。今、つっこむとこですね笑。ダンクの嫌いなところ言っていいですか。ダンクは、校正にしがみつき過ぎ。校正取られちゃうと食ってけないと思ってる節があるんです。校正でいかに商売するか、みたいな。ヒップは、全員じゃないけど、一応、校正を捨てて何ができるかっていうことと向き合って、一周戻って世間にも合わせつつ、校正を売りにしちゃったほうが手っ取り早いねっていうふうに戻ってきてるんですよ。校正をどう進化させるかという認識なので。
池田 同じ校正の使い方がちょっと違ってて。ダンクでバリバリの校正マンが校正取られちゃうと、ちょっとしんどいと思っちゃうみたいな。俺は別に校正なくたって、売れるものはあると思ってるんです。
森 出た、マウント取りにいった。
池田 校正捨てたヒップって売れなかったねというところから、ヒップの校正を売りにできるねってところに立ち返って、振り出しに戻って校正どうですかっていうのは、セールスとしては違う。
—— 津曲さんが新しいことに向かって乗り出した頃は、校正の持つ意味や役割を自ら過小評価しちゃったところもあったかも? 校正の強みを排除しても、新規開拓などから次のヒップを見いだそうといったフェーズだったでしょうか。校正から引いたようでいて、実は校正のプロセスの強みは皆さんに染み付いてるから、最終的にはその視点から今また新しいセールスの側面にいち早く気付いているともいえそうですね。
池田 結局、重宝される部分に気付いたり。そこの大事さにも気付くし、そこが分かった上で制作の発注をすると、ハンドリングがしやすかったり、客の説得力も結局ここなんだなみたいなのはある。今、ここにいる人みんな分かってるけど。対して、ダンク一辺倒で校正で評価をされてる人は、その評価が強過ぎるから、そこを奪われたときに結構あわあわするんだろうなっていうのはある。自分があわあわしたから。一回あわあわしとかないと、校正の良さっていうか、もっとアピールするとこや価値が本質的には分からないんじゃないかな。
—— 校正とひもづくブルーオーシャンとか、そういうのが。型を守って、型を壊して、型をまた育てるみたいな、そんな感じですかね。
池田 そういうことです。
校正マンの名にかけて愚直に相手の不安を消し込み、安心と引き換える。ダブルチェックをやめたときのように大胆に取捨選択して、信用と引き換える。
それはディレクションや、品質管理、スキームの立ち上げに親和するだろうし、ビジネスの新しい領域を広げ、人が全方位的に成長していく先を照らすだろう。
カスタマーインを追究して生まれたヒップ哲学
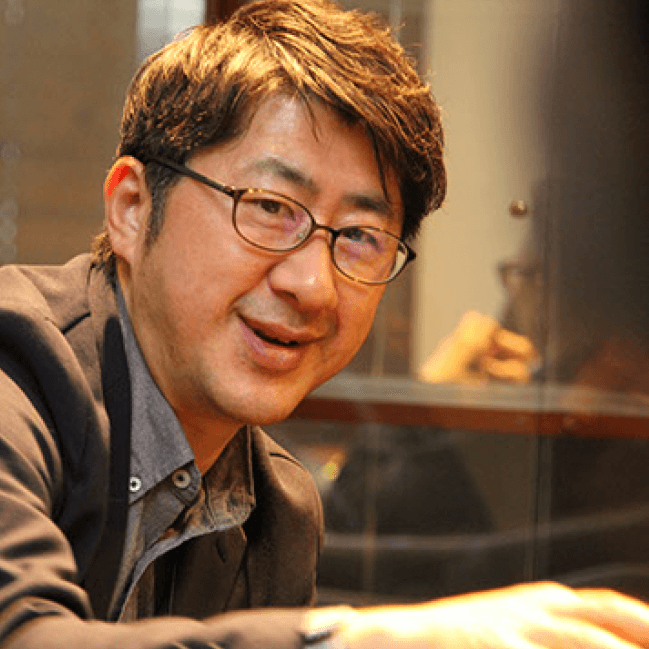
加藤 3年間で考えたヒップ哲学。答えになるか分からないですけど、「粋」ってホームページに出していて。そこに込めたのは「責任感」です。東京ヒップの仕事は、お客さんのオーダーにいかに応えていくかということから広がっていった。こっちじゃ駄目だ、あっちだ、みたいな強いリーダーシップを発揮していたかというと、そんな感じではありませんでした。むしろ、お客さんの望む落とし所は何だろうという立場から離れずに考え尽くして、「これできる?」と求められたら「ついでにこれもできます」みたいな感じで、できることや喜ばれることを増やしていったんです。これを、仕事をうまく回して相手の要望に応える責任感だと誇りたい。東京ヒップとは、「うちはここだけです」と仕事の領域を限定せずに、とりとめない要望に対して答えを探していくことで自分たちを成長させてきた会社。そう思ってます。
森 津曲さん、プロデュースって言い方してた。制作プロデュース、校正じゃなくて。これは全然、浸透しなかったんですけど。
加藤 言ってたかもしれない。そこに込めた思いは、校正だけじゃなくて、相手が求めるところで仕事つくっていきますっていう。それがヒップの仕事の考え方。
—— マーケットイン視点をさらにカスタマーインへとフォーカスして、プロセス全体の品質管理へ。それが津曲さんのいう「制作プロデュース」であり、会長のおっしゃる「編集」だったのでしょうか。それを校正のプロ集団がやるのがかっこいいです。
加藤 そうですね。これはダンクもヒップもそうですけど、自分たちがなぜやるかというと、校正を経験した人たちが、それを設計しますっていう点ですかね。
—— 課題の見つけ方とか提案の仕方も違ってきそうですね。
森 ぼくらは校正目線。間違いを間違えない前提。なので地味なんですよ。基本的には注目を浴びない。でも今思うんですけど、それで困ってる人って、意外といるんだなって。
—— そう思います。フェイクが横行しているし、簡単に文章が作れるようになってきたし。やはり、安心してもらうとか、手伝ってあげるとか、やさしい視点に立つことや責任を伴う判断は、人間が担う領域。個の経験値や現場の協働力などを積み上げてきた東京ヒップならではの裁量が、価値になってくるのでは。
加藤 確からしい答えをスラスラ出してくるChatGPTにぼくらが負ける気がしないものがあるとしたら、それは目の前の案件や個性的なテーマやニッチな案件に対して、泥臭く考え尽くせるところ。表現がちゃんとしたものかどうか、伝わるのかどうか、正しいのかどうか。正解だけじゃなく最適解や納得解をきめ細かく提示していける。それって、責任感ある粋な仕事だといえませんか。
(2023年3月8日 株式会社東京ヒップ(現ダンク)8F応接室にて収録)
ー言録・井上弘治ー
「絵画や音楽、物語(小説・映画)などを鑑賞するとき、 わたしたちは無意識のうちにその歴史と物語を見ている。 そして無意識のうちにわたしたち自身の無意識も対象から見られているのだ」
―――【2015:観(かん)】より

「現実に翻弄されることなく常に「空」を意識することは大切なのかもしれない。「空」を発見するには、智慧を必要とする。それは未来を拓くことにも通じる」
―――【2017:空(くう)】より
「わたしたちはその「網」に捕らわれてもがき苦しんでいることにまだ気付いていないのかもしれない。「見えない主催者」とは誰なのか。網目を食いちぎるほどの智慧と勇気を試される時がいずれ来るかもしれない」
―――【2018:網(あみ)】より
「虚偽の中で虚偽を暴くのは「遊びごころ」でしかない。スマホの僕のごとく画面にくぎづけになっている姿は、世界につながっているようにみえて、実は捕らえられているのだと思う」
―――【2019:遊(ゆう)】より
↑※キャプションをクリックすると……




